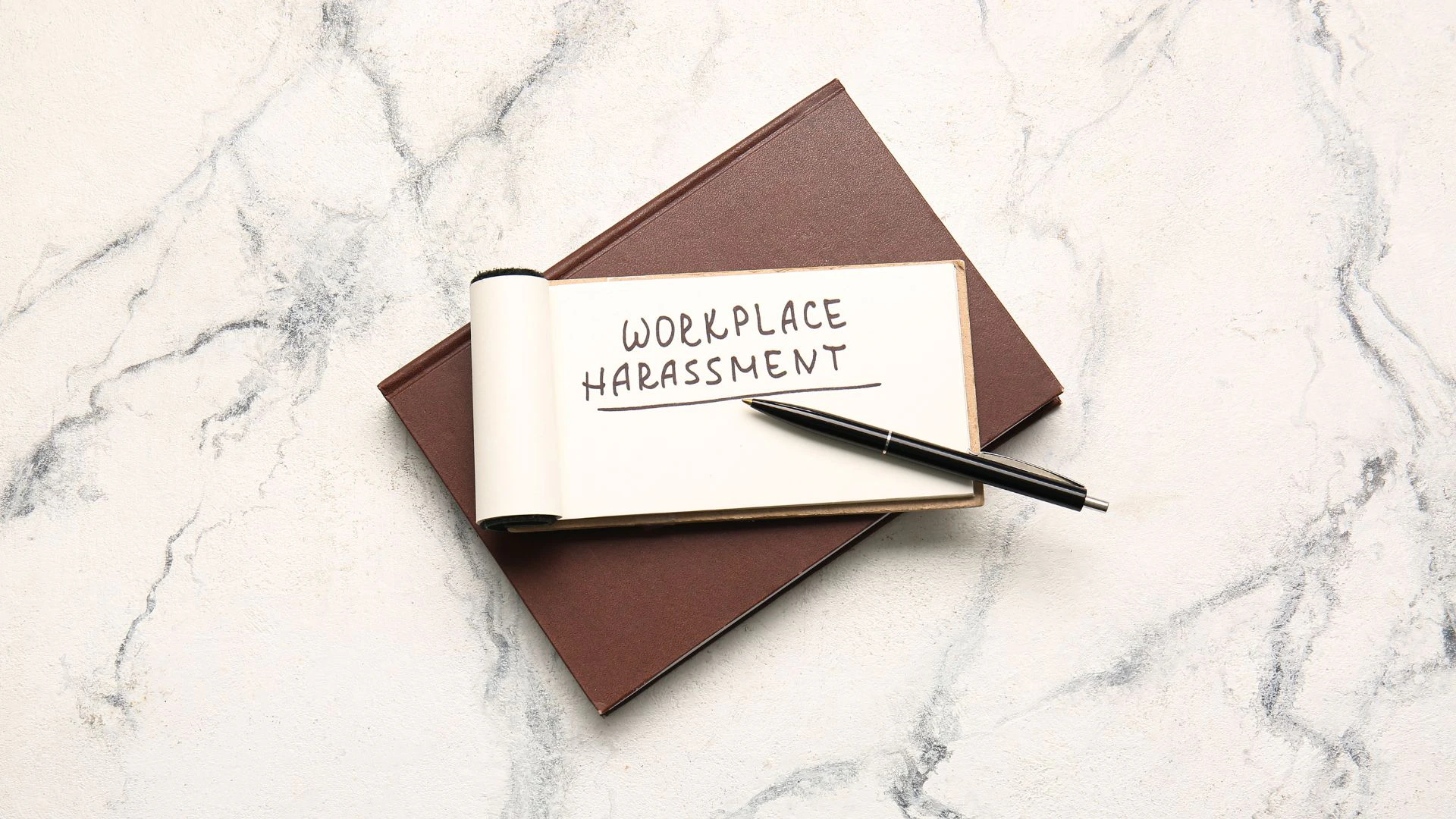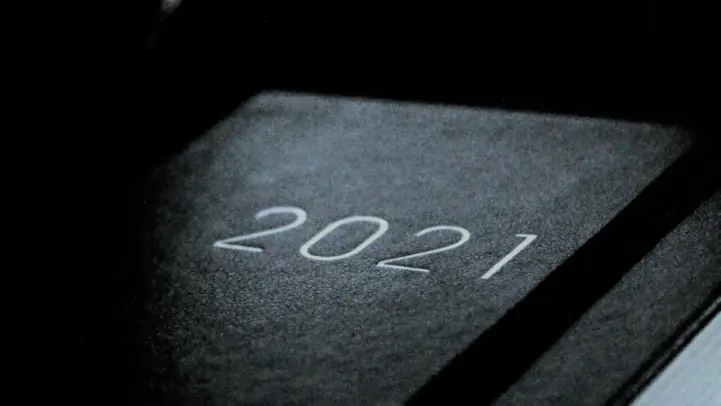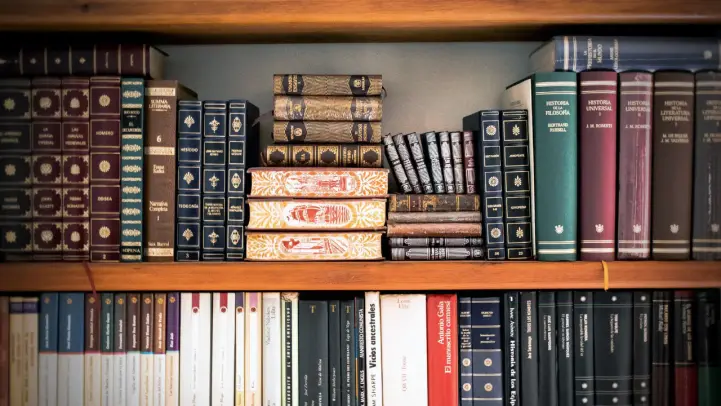今回は育児休業法(法改正事項含む)にフォーカスをあて解説してまいります。
育児介護休業法とは
育児介護休業法の第一条に目的が明示されています。
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
簡単にまとめると、育児や介護で大変な労働者が働きやすい社会を作ることを目的としているのです。
育児介護休業法は国難とも言える少子高齢化社会において極めて重要な位置づけであり、国際競争力の観点からも実効性の確保が求められます。特に近年は女性だけでなく、男性の育児休業取得率上昇が求められ、男性の家事への参加率が第2子以降の出生にも寄与するとの指摘もあります。我が国は女性の社会進出が進んでいるものの依然として女性への家事育児偏在は解消されておらず女性の更なるキャリアアップへの足枷となっている点は想像に難くありません。
職業生活と家庭生活の両立
近年は働き方改革を筆頭に旧来からの働き方から新時代への働き方へシフトチェンジが進められています。そこで「ワークライフバランス」というキーワードが一つのトレンドとなっています。
特にコロナ禍によって在宅勤務が増えたにも関わらず、女性の家事育児偏在が解消されておらず、この問題は根深い問題として今後も向き合っていかなければなりません。育児介護休業法は女性だけでなく、男性も対象とした法律であるものの、周知がいきわたっているとは言い難く、特に男性の育児介護休業法の各制度の活用が進んでいないのが課題です。
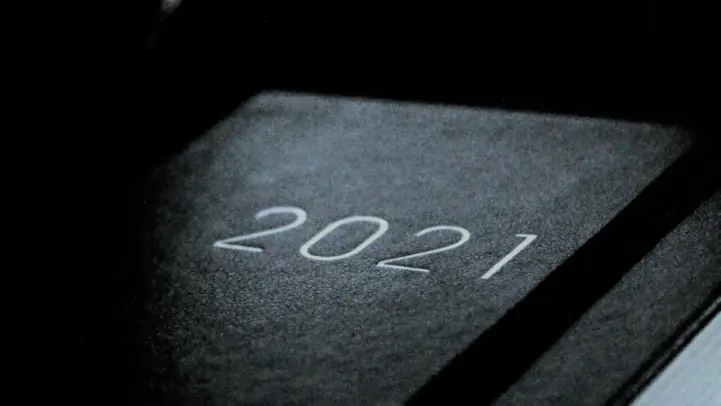
育児休業とは
原則として子が1歳になるまでの間、子の養育のために事業主に申し出ることにより取得できます。しかし、期間の定めのある労働者、労使協定によって除外することができる労働者は以下の通りとなります。
休業の定義
労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために行う休業
対象労働者
労働者(日々雇用される者を除く)、期間を定めて雇用される者は申し出時点において同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、その子が1歳6か月に達する日までにその労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでない者
労使協定で対象外にできる労働者
雇用された期間が1年未満の労働者、1年(1歳から1歳6か月に対するまでの育児休業及び1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者、子(特別養子縁組に係る子のうち一定の要件に該当する子、特別養子里親である被保険者に委託されている一定の要件に該当する子を含む)
回数
子1人につき原則として1回(パパ休暇を除く(後述))
再度の育児休業取得が可能な場合
新たな産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合、配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合、離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合、子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合、保育所等における保育の利用を希望しているが、当面その実施が行われない場合、子が1歳6か月までの育児休業については子が1歳までの育児休業とは別に取得可能
期間
原則として子が1歳に達するまでの連続した期間。ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は子が1歳2ヶ月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業(パパママ育休プラス)が可能。子が1歳に達する日において(子が1歳2ヶ月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、保育所等における保育の利用を希望しているが当面その実施が行われない場合は最長2歳までの取得が可能。

尚、育児休業中の賃金は有給であることはまで求められておらず、育児休業中の賃金は雇用保険に加入している場合、育児休業給付金として非課税で以下のとおり受給できます。
原則として育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件となりますが、支給額は休業開始時賃金日額(後述)×支給日数×給付率となります。給付率は育児休業開始日から180日が67%、181日目以降が50%となります。なお育児休業給付金を受給する際に「休業開始時賃金日額」を決定する必要がありますが、育児休業開始前6ヵ月間の給与を180日で割った金額です。
育児休業の手続き方法
事業主は証明書類の提出を求めることができます。また、事業主は育児休業の開始予定日及び終了予定日等を書面で労働者に通知します。
男女の育児休業取得率の差
育児休業の取得率については男女で大きく差が生じており、近年男性の取得率は上昇しているものの女性には遠く及びません。
雇用均等基本調査では育児休業取得率を調査しており、女性の育児休業取得率は83%であるのに対して、男性の育児休業取得率は7.48%となっております。
尚、男性が取得する育児休業の特徴として、原則として育児休業は1人の子に対して1度しか取得できませんが、妻が子を出生してから8週間以内に取得することで再度の取得が可能となります。(1度目の取得をパパ休暇と呼びます)また、パパママ育休という制度があり、夫婦それぞれで育児休業を取得することで子が1歳2カ月まで育児休業を取得することができます。
子の看護休暇とは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を事業主に申し出ることにより、負傷や疾病により当該子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして休暇を取得することができます。尚、取得することができる日数は1年度につき5労働日(対象となる子が2人以上いる場合は10労働日)であり、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者を除き半日単位で取得することができるとされています。この部分に改正が入り、半日単位だけでなく、時間単位でも取得が可能となりました。よって、更なる取得を促そうということです。
また、子の看護休暇は取得の申し出を拒むことはできません。しかし、労使協定により一定の範囲の労働者を定めた場合はこの限りではありません。例えば交代制勤務による業務がその一例です。尚、休暇当日の申し出であっても使用者に権利として時季変更権が認められているわけではありません。これは、そもそも子の疾病などは突発的に発生する場合も多く事前の申請が難しいことが挙げられます。

改正事項と就業規則変更の際の留意点
子の看護休暇に関わらず法改正が行われた場合は就業規則の改定が必要となります。改正内容としては「1時間単位」での取得が可能である点と、取得可能な対象は「全ての労働者」であることです。尚、時間単位の「時間」とは1時間単位のことを指し、労働者からの申し出に応じて希望に沿った取得をさせなければなりません。
午前と午後で所定労働時間が異なる場合
新たに時間単位取得が可能となる労働者は今後、半日単位の取得を認める必要性は乏しいと考えます。今後も継続して半日単位も含めて運用していく場合は、例えば所定労働時間が午前3時間、午後5時間の事業場の場合、午前に2回取得で1日分として扱う運用は不適切となります。1時間未満の端数が生じて午前と午後を分割する場合は分単位での取得も可能とし、午前と午後の取得による不利益が生じないようにすることが求められます。
取得が進まない背景
子の看護休暇の取得が進まない背景としてそもそも給与保証のある年次有給休暇の取得が進んでいないことが挙げられます。子の看護休暇は有給であるか無給であるかは規制がなく、あえて子の看護休暇を取得するのではなく、有給休暇を取得していることが挙げられます。

育児休業のその他事項
不利益取り扱いとは
育児介護休業法は不利益取り扱いの禁止として以下の条文が定められています。事業主は労働者が育児休業の申し出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
後述する男女雇用機会均等法および育児介護休業法の不利益取扱いの判断の要件となっている「理由として」とは、妊娠、出産、育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に因果関係があることを指しています。
そして、妊娠、出産、育児休業等の事由を契機として不利益取扱いを行った場合、原則として「理由として」いると解されます。原則として、妊娠、出産、育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は契機としていると判断します。しかし、事由の終了から1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている場合や、ある程度定期的になされる措置 (人事異動、人事考課、雇止めなど)については、事由の終了後の最初の当該措置の実施までの間に不利益取扱いがなされた場合は契機としていると判断します。
男性が育児休業を取得する場合のメリット
一つは女性の家事育児偏在の解消です。また、社会保障制度活用の観点から、女性同様に育児休業期間中の社会保険料免除制度が活用できます。同期間中は保険料納付済期間と同様の期間として扱われ、将来受け取る年金額も減額されることはありません。
また、雇用保険からは育児休業給付金が支給されます。(育児休業期間中が有給扱いの場合は支給されない)
属人化の解消
育児休業等を取得すると言うまでもなく育児休業等を取得する労働者が担っていた業務の分担が必要です。
業務分担のプラス面として俗人化の解消が挙げられます。俗人化は万が一特定の業務を担っていた労働者が退職や疾病等による長期休業となった場合、代替できる労働者が育っていないことから業務に支障が出てしまいます。業務フロー等も共有されていない場合もあり、ミスの温床となることも珍しくありません。
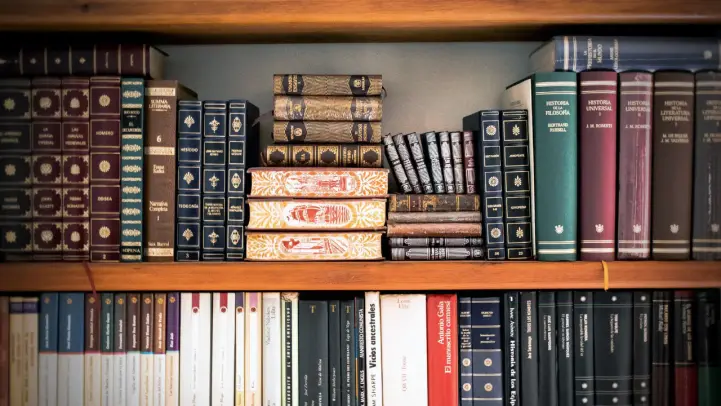
離職率の低下
育児介護休業法が整備される前は妊娠等により退職せざるをえない労働者は多数存在していました。育児介護休業法の誕生により旧来退職を選択していた層が雇用関係を継続したまま育児に専念することができる土壌が整備されました。
しかし、育児介護休業法の改正内容や制度そのものの周知が十分になされているとは言い難い状況です。
男女雇用機会均等法
育児介護休業法と共に差別的取り扱いを禁止する法律として男女雇用機会均等法があります。同法では事業主は労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
また「間接差別」の禁止として、男性および女性の比率その他の事項を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては当該措置の対象となる業務の性質に照らして業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして合理的な理由がある場合でなければ講じてはならないとされています。
周知
育児介護休業法は労働基準法と同様に労働関係法令に分類されますが、労働基準法等と異なり、罰則も少ないことから、周知が行き届いていないケースも散見されます。

最後に
育児介護休業法は育児休業と同時に介護休業についての規定も整備されています。子供の数が減り、高齢者の数が増える現在の日本の状況では介護休業についても注目されるものと考えます。
特に人事労務担当においては、従業員の相談窓口を担うこともあり、制度の理解と発信が求められます。