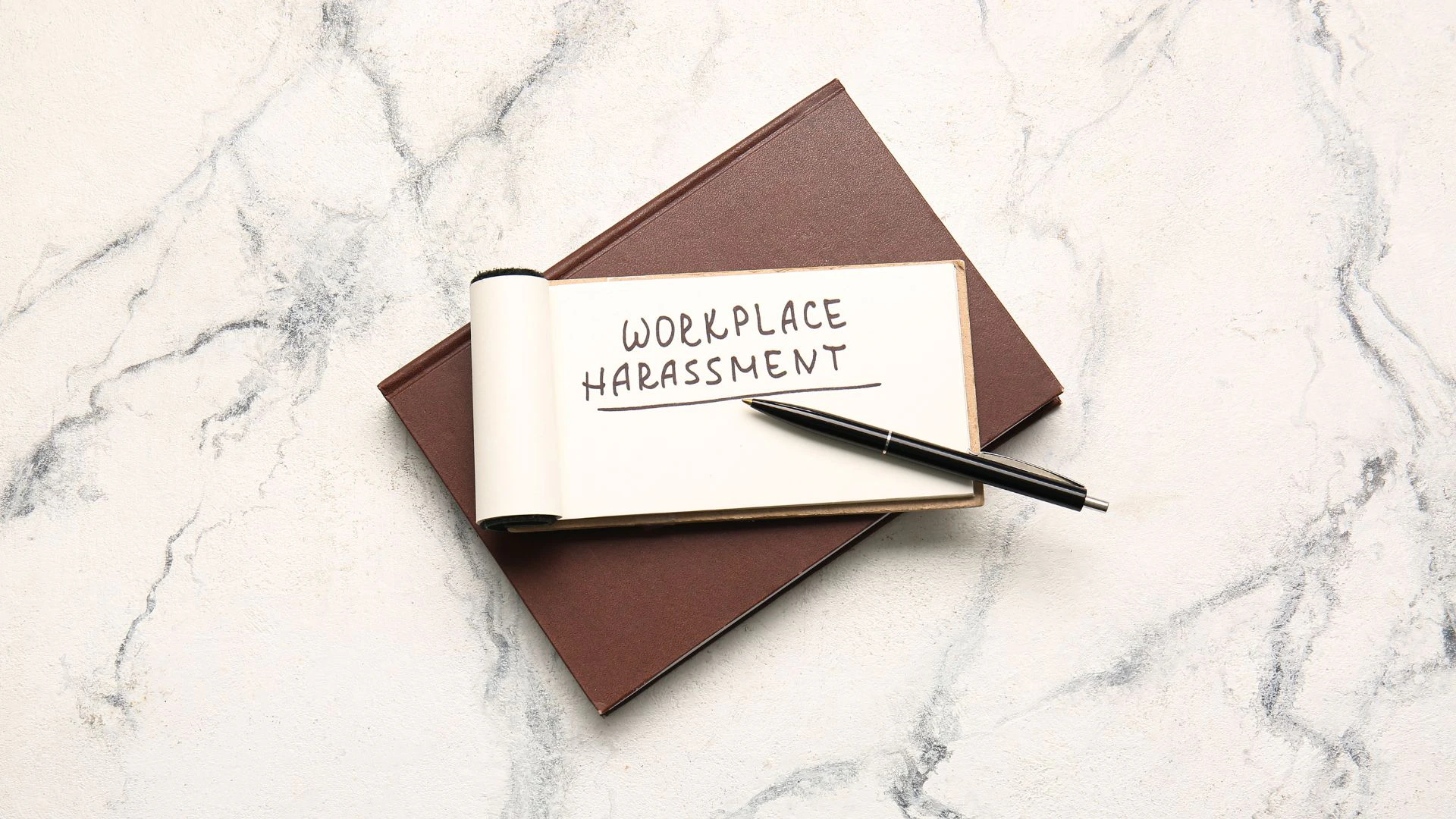テレワーク導入にあたって
まずはテレワークの形態を確認しましょう。大きく分けて3つの形態があります。

在宅勤務
1つ目は在宅勤務です。テレワークとは端的には「離れた場所で働く」ことを指しています。その中でも最もポピュラーな形態と言えます。言うまでもなく、起居寝食をする自宅で仕事を行うことで通勤時間が発生しないことから、感染リスクも最大限低減でき、子供の養育をしながら働くビジネスパーソンにとっては非常に相性の良い働き方とされています。ゆえに仕事と家庭生活の両立がしやすい制度と言えます。
サテライトオフィス
次にサテライトオフィスでの勤務が挙げられます。サテライトオフィスとは職場と自宅との中間地点等に設けられたオフィスを指します。この中には、シェアオフィスやコワーキングスペースも含まれます。在宅勤務には及びませんが多くの従業員の通勤時間が短縮され、在宅勤務以上に作業環境が整った環境で働くことが出来る点はメリットと言えます。
モバイル勤務
最後にモバイル勤務が挙げられます。モバイル勤務とは従業員が自由に働く場所を選ぶことができ、カフェ等で行われることがあります。よりリラックスできる環境下で働くことができ、(例外なく全員にあてはまるメリットとまでは言えませんが)独創的なアイデアが生まれやすいなどのメリットが挙げられます。
テレワーク下における労務管理上の留意点
留意点としては3点ありますので以下にご紹介します。

導入目的
まずは、どのような「導入目的」でテレワークを行うのかに着目すべきです。多くの場合、感染予防対策や、政府の要請、同業他社の動向を鑑みてテレワークを導入するという外部要因によって導入を決断した企業もあるでしょう。目的が不明瞭であれば、今後の選択も誤ってしまうことがあるため、明確化しておくべきです。単純に感染者数のみで一律に安全とは断言できませんが、予め会社所在地の感染者数が一定人数を下回ったら段階的に対面業務を再開するなどの方針を示しておくことで、いざ全面的に対面業務に戻す際の従業員の納得感は得やすくなります。もちろん、導入目的と併せてどのような場所での実施を想定(または認める)しているのか(例えば感染予防対策が目的であれば、都心部のカフェより在宅の方が望ましい)、その際の費用負担も労使間での協議が重要です。
対象業務
次に「対象業務」です。エッセンシャルワーカーを始め、業態的にテレワークが困難な業務も存在します。例えば医療業などはその典型例です。本人の職業倫理を尊重し、対象業務を示さず、一部の職種だけテレワークを実施させるという方針は「あえて言うまでもない」との考え方もありますが、人事部門として一定の考慮をしていることを示す意味と、労使間の確認的な意味合いでもテレワークの対象となる業務は示すべきです。また、最近では、テレワークと対面業務のハイブリッド型の労務管理が増えており、水曜日と金曜日のみ出社するなど、テレワークの対象となる日を示しておくことで、労使双方に、業務の見通しが立てやすくなります。
対象労働者
最後に「対象労働者」です。対象業務と同様の意味も含まれていますが、例えば、同じ対象業務であっても、まだ業務の習熟度が低く、独り立ちする前の新卒社員は一定の教育期間を経た後に対象労働者に含めるという労務管理体制を敷く場合があります。その場合も予め対象労働者を明らかにしておくことが適切です。
テレワーク実施時の費用負担
テレワークを実施するために従業員に過度な負担が発生する状態は望ましい状態ではありません。会社から貸与可能な物がある場合は新規に購入する必要性は乏しいですが、そもそも自宅とは仕事をする環境を想定して設計されていませんので、オフィスよりも生産性が落ちるのが一般的です。しかし、その生産性の低下が許容できない程度であれば新規に物品を購入する必要性が高いと言えます。その場合は会社が費用負担するのが一般的です。しかし、制限なしに認めてしまうと業務の性質と比較してあまりにも高性能な機器を購入してしまう場合もあるため、会社が先行的に購入するか、従業員が購入後に費用負担するのであれば請求方法と併せて価格の上限を設定しておくことがよいでしょう。
また、従業員に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる場合は就業規則に規定しておかなければなりません。
自社で取り得るテレワークのルール
まずはテレワークであっても、働いてもらうことには変わりありませんので、予めテレワーク規程を整備し、自社にとって、履行してもらいたいルールを周知しておくことがスタートとなります。

働く場所
最も重要な部分としては働く場所です。例えば、テレワーク実施労働者の業務が機密情報を扱う場合に、カフェで仕事をするのは避けてほしいということであれば、「会社が許可する場所」でテレワークが可能との条文を設けておくことが適切です。そうすることで、会社の想定外の場所で業務を行うという認識齟齬は回避できるでしょう。
最低賃金法
また、企業の履行が義務付けられる「最低賃金法」について確認しましょう。テレワーク実施場所に関わらず、テレワークを行う従業員の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されますので、例えばテレワークを期に他の都道府県へ転居した労働者に対して最低賃金と密接した額で労働契約を締結している場合、予め認識を合わせておくことがトラブル防止の為にも有用です。
雇用契約書
次に雇用契約書上の注意点です。雇用契約書には働く場所の明示も必要です。よって、テレワーク規程同様に、「会社が許可する場所」と記載することや、テレワークを在宅勤務に限定するのであればその旨を記載するなどの選択肢が挙げれます。また、雇用契約締結時において、会社として労務の提供場所の見通しが立っていない場合には、テレワークを行う場合がある旨とテレワーク実施場所を記載しておくことが望ましい状態です。もちろん、雇用契約の内容自体を変更する場合には労使合意の元、変更する必要があります。
自社で取り得る労働時間制度と管理方法

通常の労働時間制
通常の労働時間制の場合、単に働く場所がオフィスから自宅等に変更になった状態であり、始業および終業時の時刻はオフィスで働く場合と同様に扱います。また、運用していく中で、従業員ごとに始業および就業の時刻の調整を認める場合には、それを認めること自体は問題ありません。しかし、深夜(22時から翌朝5時)に働いてしまうと、深夜割増の支払義務が生じることから会社の許可なく深夜帯に働くことがないように周知しておくことが適切です。
変形労働時間制
通常の労働時間制と同様に予め始業および終業の時刻を定めておく必要があります。深夜の割増についても通常の労働時間制と同様の考え方となります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは始業および終業の時刻を従業員自身が決定できる制度で、いずれか片方だけ決定できるという状態はフレックスタイム制ではありません。フレックスタイム制は、柔軟な働き方の代表的な制度であり、仕事と生活の調和を図ることができる制度です。一時的に業務を離れる「中抜け」についても認めること自体は可能です。注意点としては、その時間は労働時間ではありませんので、どのように取り扱うかを決めておく必要があります。時間単位の年次有給休暇や終業時刻を繰り下げて働くことでトータルの労働時間を同じにするなども多く用いられている選択肢です。
また、フレックスタイム制にはコアタイム(従業員が働かなければならない時間帯)を設けることができますが、テレワークの日にはコアタイムを設けず、オフィスへ出社する日に限ってコアタイムを設けるという選択肢もあります。尚、フレックスタイム制であっても、深夜割増は無視できませんので、注意が必要です。
事業場外みなし労働時間制
従業員が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難な場合に適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督がおよばない事業場外で業務に従事することとなる場合に選択可能です。実務上、判断が難しい部分は「情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」との要件があります。この部分に対しては、労働時間中に従業員が自らの意思で情報回線自体を切断することができる状態または通信回線の切断はできないが、情報通信機器から自らの意思で離れることができ、応答のタイミングを従業員が判断できる場合には要件を満たすという解釈です。
次に他の要件として「常時使用者の具体的な指示に基づいて業務をおこなっていないこと」との要件があります。この部分については業務の指示が基本的事項に留まり、作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合には要件を満たすという解釈です。
尚、「情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」と「常時使用者の具体的な指示に基づいて業務をおこなっていないこと」は、いずれの要件を満たしておくことで、制度を適用させることが可能となります。
テレワーク下の安全衛生
労働安全衛生法では、安全衛生管理体制を確立し、職場における従業員への安全と健康を確保するために必要となる具体的な措置を講じるように求められています。自宅等でテレワークを実施するにあたっても関係法令に基づき従業員の安全と健康を確保するための措置(例えば長時間労働が窺われる従業員に対して面談の機会を設ける)を講じる必要があります。テレワークは直接顔を見れるオフィスでの勤務以上に従業員の健康状態の変化が確認しづらいという点は否めません。
テレワーク下の労働災害
テレワークを行う際にもオフィスでの勤務と同様に使用者が労働災害に対する補償責任を負うこととなります。テレワークは労働契約関係に基づき使用者の支配下にあることによって業務が行われることから、業務上の災害であった場合、労災保険給付の対象となります。しかし、私的行為中の負傷は原則として業務災害にはなりません。
テレワーク下のハラスメント対策
テレワーク下であってもハラスメントが全くないとは言えません。オフィスでの勤務と比べると直に上司等と接する機会は減りますが、Web会議内での必要相当程度を超えた指導には十分注意を払う必要があります。特に在宅勤務でのWeb会議となると主目的が生活の場である自宅内で業務に関する打ち合わせを行うことから、背景に映り込む空間を懸念することもあるでしょう。その場合に背景をぼかす設定をすることや、一時的に子供と同じ空間で在宅勤務を行わざるを得ない場合に、他の会議参加者への配慮からミュート設定することも考えられます。それらを禁止するという判断はさすがに無理があります。Web会議での注意点として、オフィスでの会議と異なり、個室で個別に指導するということが難しく、多くの参加者の前で注意することになるため、言葉の選択やボリュームには注意を払うべきです。

テレワーク下のセキュリティ対策
セキュリティ対策については従業員ごとに知識量に差があることも珍しくなく、企業がガイドライン等を活用し、先陣を切って示していく必要があります。しかし、交通事故や感染症への感染と同じくセキュリティ面においてもリスクゼロにはなりません。その点を踏まえてどのようにしてリスクを低くできるかという点にフォーカスをあて社員教育を行っていくことが有用です。また、会社としてかけられる費用にも限界がありますので、費用対効果を踏まえた対策が現実的です。