| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | Remoba労務 |
会社名 | (株)Enigol |
対応メニュー |
上記以外の業務を承ることも可能です。お気軽にご相談ください。 |
詳細 |
|
公式サイト | https://remoba.biz/hr |
労働者が企業に雇用され労務の提供をしていくにあたっては双方の合意のもとで労働条件を決定する必要があります。しかし、withコロナ時代においては、将来的にも不透明な時代背景となり、やむを得ず当初定めた労働条件を変更するという決断に迫られるケースも珍しくありません。


労働者が企業に雇用され労務の提供をしていくにあたっては双方の合意のもとで労働条件を決定する必要があります。しかし、withコロナ時代においては、将来的にも不透明な時代背景となり、やむを得ず当初定めた労働条件を変更するという決断に迫られるケースも珍しくありません。
今回は、労働条件変更にフォーカスをあて解説してまいります。
常時10人以上の労働者を使用する場合は所轄労働基準監督署長へ就業規則を届け出なければなりません。よって、常時10人未満の労働者を使用する場合、就業規則の届け出義務はありませんが、トラブル防止の観点から作成している事業場も多く見られます。
また、就業規則とは別に個別の労働契約を締結しており、就業規則と内容が異なっている場合もあります。その際、どのように整理すべきでしょうか。
まずは、効力の上下関係は労働契約よりも就業規則の方が強くなります。そして、就業規則は他の要件(周知等)を満たしていることが前提となりますが、最低基準効があります。これは、就業規則に定める条件はその事業場の最低基準となり、それを下回ることができません。よって、あまりにも高水準な待遇を規定してしまうとその後の運用が苦しくなってしまうということです。
就業規則と労働契約で内容が異なっている場合には、当然、就業規則を下回る労働条件は最低基準効により無効となりますが、個別合意により就業規則を上回る労働条件で合意している場合は無効とはなりません。よって、労働契約を定める場合は就業規則と同等または就業規則を上回る内容は無効とならず、就業規則を下回る内容の場合は無効になるということです。

労働条件と言っても賃金や労働時間などの重要な労働条件から幅広く存在します。withコロナ時代においては先行きの不透明感が際立ち、現在の労働条件を終身にわたって保証し続けることは困難な場合もあるでしょう。
そこで、労働条件を変更する場合には以下の点に注意すべきです。言うまでもなく変更の合理性の要件を満たさなければなりません。
・労働者が受ける不利益の程度
・変更の必要性
・内容の相当性
・経過措置の有無
・交渉の経緯
・一般的状況
また、労働者に対して労働条件の変更を打診する場合は一定の時間的猶予を与えることが必要です。これは、変更に同意したと言っても時間的余裕がなかったためにやむを得ず同意した場合、真意に基づいた同意とは言い難く、後で問題となる場合がります。
よって、労働条件変更を打診した場合、その日のうちに回答を得ようとすることは得策ではありません。時間的猶予は労働者に熟慮する時間を与え、万が一応じないとなった場合は、個別の労働条件を締結するなどが考えられます。また、労働条件の変更に応じなかったからと言って解雇に踏み切るのは短絡的です。

賃金の変更は労働者にとって生活に与える影響が高く、高度の必要性がなければ難しいと言えます。必要性を基礎づける事実として常に営業収支等が黒字である場合、そもそも業務上の必要性があるとは言えません。
しかし、赤字続きで経営的にも危機的状況が近づいてきた場合は許容されると考えますが、引き下げる目安としては労働基準法第91条を参考にするのも選択肢であると考えます。同法は減給の制裁規定であり、減給する場合は一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとされています。しかし、減給の制裁規定は懲戒処分を科す際に用いられるもので、必ず10分の1以内にしなければならないということではありません。
対象者を決定する際においても例えば労働組合員のみ引き下げ対象とするという判断は無効とされる可能性が高まります。特定層のみを不利益変更するのではなく、応分に負担をするということであれば、無効とされるリスクは低減できると考えます。
また、労働組合があれば労働組合と交渉をし、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者と交渉をする必要があります。全く交渉をせず、不利益変更を行うとなるとそもそも同意を得ようする姿勢すら感じられず、納得感を醸成することは不可能に近いと言えます。
実際に不利益変更を行うと決定した場合であってもいきなり今月から行うという判断は適切ではありません。労働者に周知し、数か月後から実施するなどの経過措置は必要です。
また、労働条件の変更を行う場合は就業規則を改訂しなければなりません。当然、就業規則の最低基準効は無視できず労働条件と就業規則が乖離した状態は適切な労務管理とは言えません。
さらに、基本給以外の手当の不利益変更についても生活に与える影響は無視できないことから上記の手順を踏むことが求められます。

賃金と並び重要な労働条件である労働時間も業務上の必要性等が求められます。
しかし、賃金の変更と異なる部分があります。例えば所定労働時間の短縮や休日日数の増加は労働者にとっては有利な変更となります。しかし、それに伴い賃金が減少してしまうとなるとその部分は不利な変更とも言えます。よって、賃金減額が紐づく労働時間の変更については高度な必要性が必須と言えます。
また、所定労働時間を延長させる変更を行った場合、旧来支払われていた残業代が支払われないとの議論も起こり得ますが、そもそも時間外労働は使用者が命じるものであり、労働者にとって不利益変更とは言い難いと考えます。
また、朝と夕方の時間帯に繁忙を極める事業所において昼間の休憩時間を延ばすことで、労働時間自体は延ばさずに必要な労働力を確保するということもありますが、「拘束時間」は延びることから労働者の合意と必要に応じて一定の手当を支給するなどの選択肢が想定されます。
就業規則に始業または終業時刻を変更する可能性がある旨の規定をおいておくことで労働者の予見可能性を担保した状態と言えます。
しかし、育児介護休業法等を含めて総合的に勘案すると、子を養育する労働者にとっては、始業および終業時間の変更は労働者の生活に大きな影響を与えることがあり、配慮しておくことが適切と考えます。
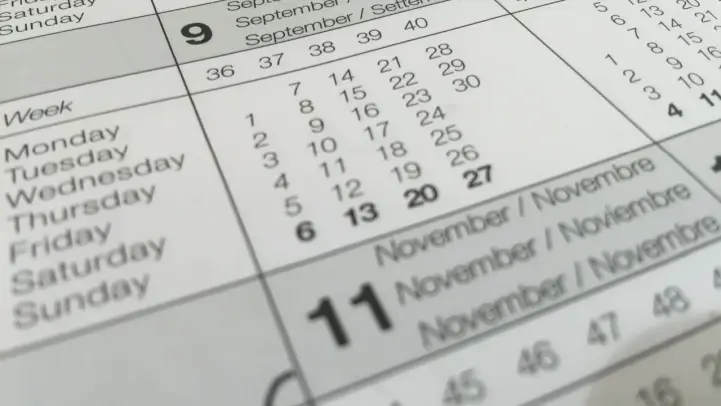
年間休日を減少させると総労働時間は増加します。そこで、賃金額が変更なしとなる場合、賃金単価は引き下がったことになりますので、不利益変更に該当します。よって、代償措置を講ずるなどの対応が必要です。
例えば基本給20万円の労働者に対して基本給を18万円に減額し、固定残業代〇時間分として2万円とした場合、総額は維持されているように見えますが、変更前は基本給20万円プラス残業が発生すれば残業代が支給されていました。しかし、変更後は〇時間分の残業代は追加で支給されなくなることから不利益変更に当たります。
また、賞与を計算する際に基本給に対して支給率を乗じていた場合には当然賞与の支給額も減額することから不利益の程度は大きいと言えます。
変形労働時間制の導入は通常の労働時間よりも労働時間が不規則になります。よって、生活に与える影響を考慮すると不利益変更とも言えます。しかし、総労働時間が減少するのであれば直ちに不利益変更とは言えません。
また、フレックスタイム制はそもそも労働者にとって有利な制度(労働者が始業および終業の時刻を決められる)であることから、不利益変更の問題は生じません。
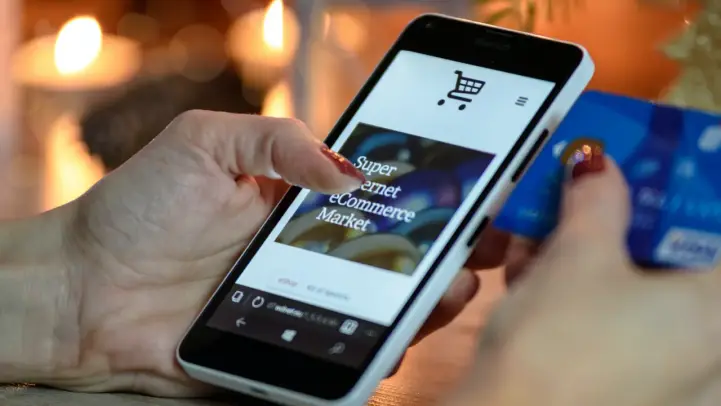
まず、労働基準法に休職に関する規定はありません。しかし、多くの企業で休職制度を採用しています。
また、休職規程の変更については、賃金や労働時間と異なり、休職という性質上、全労働者が定例的に享受するものではないことから、不利益の程度は小さいと考えます。よって、労働者への説明や経過措置(一定期間経過後に導入する)を採用することで、不利益の程度は小さくできると考えます。
本来、労働契約締結の際に取り交わした内容の労務の提供ができない場合は債務不履行により解雇事由にあたります。しかし、長く働くということは、その間に負傷または疾病などにより一時的に労務の提供が困難となる場合もあるでしょう。そこで、一定期間労務の提供を免除し、労務の提供が可能となったタイミングで復職できる制度を導入(休職制度)している企業が多く存在します。当然、休職期間中は労務の提供は免除されており、かつ、労働契約関係自体も消滅していないことから、一定の身分は保証された状態と言えます。
近年は外見上判別がつきづらい精神疾患などを理由とした休職も多くなっており、また、同疾患は再発の可能性も高く、一定の事由に該当した場合は復職を認めないとする規定の創設が想定されます。また、復職に際して会社が指定する医師の診断を受診することを命じる規定を盛り込むなども適切です。
使用者にとっても労務の提供を受ける時点で安全配慮義務が無視できなくなり、労務提供が不完全な状態は業務上望ましいことはもちろんですが、業務上一定の負荷が生じた結果心身に重大な悪影響を与えてしまった場合には責任問題にまで発展する可能性もあります。
また、リハビリ勤務の創設または変更についてはリハビリ勤務自体が債務の本旨に従った労務提供ではありませんが、事実上の指揮命令関係が生じている場合は賃金支払い義務が発生しますので注意が必要です。

個別の労働契約書を取り交わしたあとに労働条件を変更するとなった場合は、再び労働契約書を取り交わすとなると、事務負担が大きいことから、覚書を取り交わすのが一般的です。また、覚書を作成する際には、変更する労働条件、変更時期などを明確にし、双方で認識齟齬が起こらないよう注意すべきです。
労働条件を変更する際には労働者へ周知しなければなりません。就業規則の変更で労働条件を変更する場合は、作業場ごとに就業規則をいつでも見られる状態にしておくことが求められます。
労働者の就労場所を変更することを配置転換と呼びます。様々な人事施策により配置転換はなされますが、判例からの学びとして企業には配置転換においては一定の裁量が認められています。しかし、転居を伴う配置転換の場合は業務上の必要性があること、不当な目的(例えば退職に追い込むことを画策する)でないこと、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでないことの要件を満たす必要があります。
尚、労働契約締結時に職種限定または勤務地限定の合意が形成されている場合、合意している内容以外の職種または勤務地への転換を命ずる場合は、労働者の合意が必要であることは言うまでもありません。
また、配置転換を命ずる場合は原則として会社の裁量で行われるものですが、病気療養中の労働者や幼児を養育する労働者等については一定の配慮が必要です。

恒常的に労働条件の不利益変更案が起こる場合は、そもそもの制度設計に無理があるのかも知れせん。労働条件の不利益変更は労使双方にとって歓迎されるものではなく、恒常的に行うとなると労使間の信頼関係に亀裂が生じます。
また、制度設計そのものを見直す場合は、猶予期間の設定や代償措置を入れるなどの配慮は必要です。
労働条件の不利益変更を行うにも関わらず好待遇での求人をかけている場合、労働者の納得感を得ることは困難と言えます。特に有料求人サイト等に募集を掲載している場合は尚、厳しいものと考えます。
人件費過多のため、労働条件の不利益変更に舵を切る前に他に目を向けるべき部分があります。例えば慢性的に長時間労働となっている企業の場合、労働条件の不利益変更を行う前に時間内に業務を終えられるような人員調整ならびに社員教育に時間をかけることで、労使双方にダメージの大きい労働条件の不利益変更に舵を切らなくても良い場合があります。長時間労働は好待遇での労働条件以前に心身を蝕み、家族と過ごす時間も少なくなり、デメリットが非常に大きなものです。


Remoba労務は、労務クラウドサービスの導入・運用をオンラインワーカーが担うアウトソーシングサービスです。
人事・労務の実務経験者を中心とした、オンラインワーカーのチーム制で、労務を丸ごと代行します。入退社の手続きや勤怠管理、給与計算、年末調整、健康診断の案内など、幅広くカバー。業務は独自マニュアルや管理ツールで可視化されるため、属人化やミスを防止して品質を確保しながら、業務効率化が可能です。
複数のクラウドサービスを活用してWeb上で資料回収・提出を行うため、データのやり取りもスムーズ。リモートワークをはじめとした、柔軟な働き方ができる職場環境の構築も支援します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | Remoba労務 |
会社名 | (株)Enigol |
対応メニュー |
上記以外の業務を承ることも可能です。お気軽にご相談ください。 |
詳細 |
|
公式サイト | https://remoba.biz/hr |
労働条件の変更は長期雇用が前提の企業の場合は、一度は直面することでしょう。注意すべき点はこれまで述べてきましたが、変更の必要性等を基礎づける理由が必要です。特に労働条件の中でも生活に与える影響の大きい賃金等は慎重に対応すべき部分です。

株式会社Enigol
株式会社リクルートホールディングスでWEBマーケティング業務および事業開発を経験し、アメリカの決済会社であるPayPalにて新規事業領域のStrategic Growth Managerを担当の後、株式会社Enigolを創業。対話型マーケティングによる顧客育成から売上げアップを実現するsikiapiを開発。