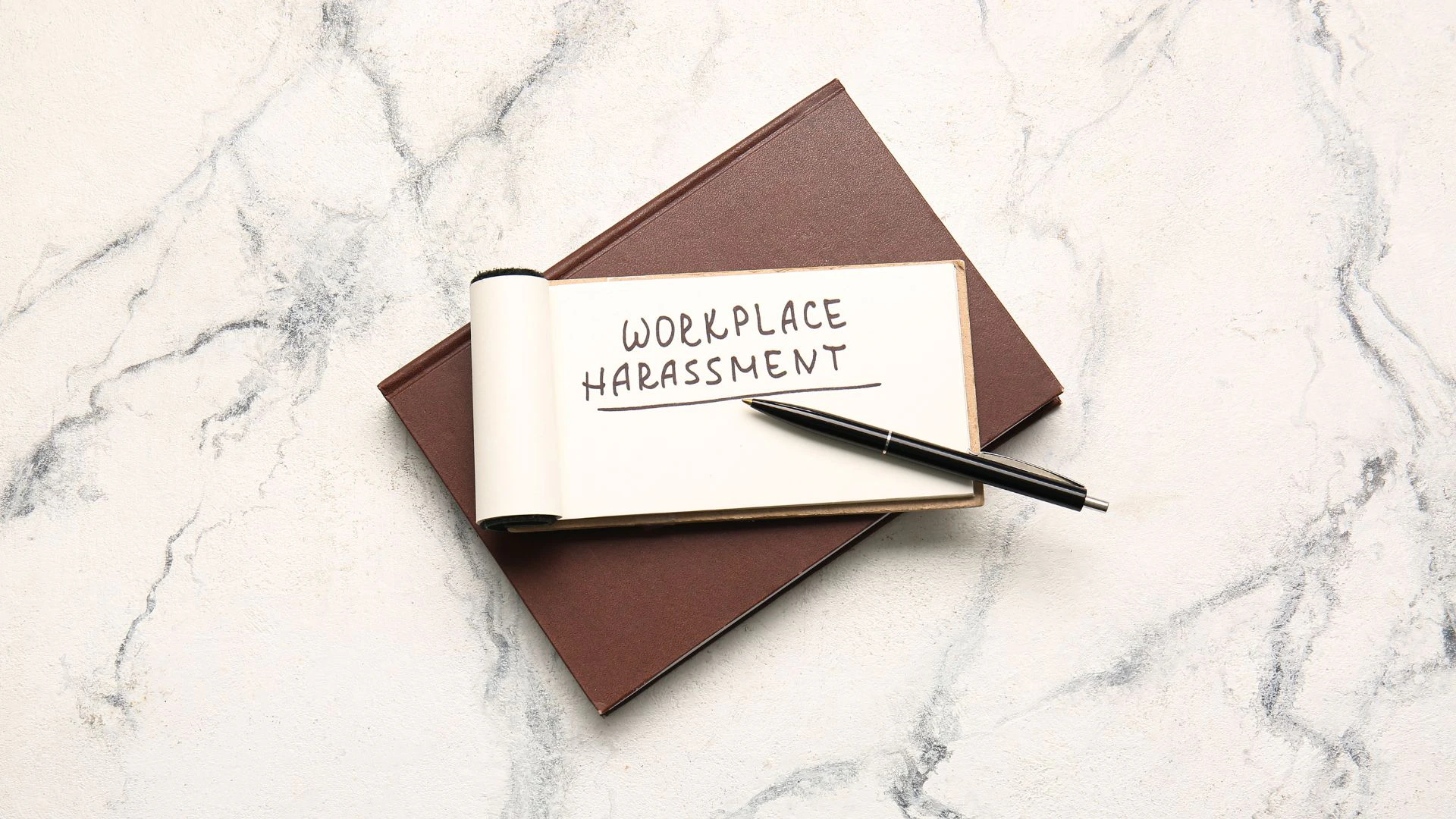今回は労使双方に注目度の高い休暇に焦点をあて、解説してまいります。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働者がライフイベントによって労務の提供が困難になったり、心身ともにリフレッシュしたりする際に、使用者から賃金が支払われる休暇日のことです。毎年一定の日数が付与されていますが、取得率の低さが問題になったりもします。さらに有給休暇について詳しく見ていきましょう。
年次有給休暇の発生要件
労働基準法で規定する年次有給休暇は6カ月継続勤務し全労働日の8割以上の出勤率があれば10日の年次有給休暇が付与されます。これは労働条件の最低基準たる労働基準法で規定されたものであり、就業規則や労働契約で法を下回る取り決めをし、労使双方が合意したとしても無効となります。
尚、全労働日とは労働契約上労働契約の課せられている日を指します。原則として一年間の総歴日数から就業規則等で定められた所定休日を除いた日数となります。また、全労働日に含まれない日が以下のとおりです。
・所定休日に労働させた日
・不可抗力による休業日
・使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日
・正当な同盟罷業(ストライキ)その他争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
・代替休暇を取得して終日勤務しなかった日

逆に、実際には出勤していないものの、出勤したとみなす日が下記のとおりです。
・業務上(通勤災害は含まれない)負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・女性が産前産後休業した期間
・育児または介護休業した期間
・年次有給休暇を取得した日
・労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日
実務上の注意点として、女性が出産予定日よりも遅れて分娩し、結果的には産後6週間を超えた場合の休業は出勤率の算定にあたっては出勤したものとみなして取り扱わなければなりません。
有給休暇の付与日数
フルタイムの労働者の場合、年次有給休暇の発生要件を満たしている場合は6ヶ月経過時に10日付与され、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、そして以降1年経過するごとに2日増えていき、6年6ヶ月で20日が付与されることとなります。尚、入社後6ヶ月から1年6ヶ月経過時点では8割以上の出勤率がなかった場合、有給休暇は発生しませんが、1年6ヶ月から2年6ヶ月経過時点で8割以上の出勤率がある場合には2年6ヶ月経過後に発生する有給休暇は11日ではなく、12日となります。
アルバイトの有給休暇
パートなど、フルタイム労働者よりも労働時間が短い労働者の有給休暇はどのように考えるべきでしょうか。
比例付与と言いフルタイム労働者よりも付与日数が少ない形で有給休暇を与えることができます。そして、比例付与の対象者は以下の条件となります。
週の所定労働時間が30時間未満
かつ
週の所定労働日数が4日以下、または週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間の所定労働日数が216日以下の者
週の労働時間と週の所定労働日数いずれも満たしていなければならず、例えば週の所定労働時間が30時間(又は週5日労働)の場合は対象外という理解です。
実際に付与する日数の計算方法は以下のとおりです。
通常の労働者の有給休暇の日数×比例付与対象者の所定労働日数/通常の労働者の所定労働日数(5.2日)
例:働き始めて1年で一週間に3日の労働者 10(日)×3(日)/5.2(日)=5.7(日)
少数点を切り捨てて、5日の有給休暇が比例付与されます。
計画的付与
労使協定を締結することが前提となりますが、労働者の有給休暇の(繰り越し分も含めて)5日を超える部分について、定め(例えば年末年始の所定休日の前日を計画的に付与する)により有給休暇を与えることが可能です。
有給休暇時季指定義務
2019年4月1日より企業規模を問わず年10日以上有給休暇が付与される労働者には1年以内に5日の有給休暇を付与しなければなりません。また、使用者としては労働者に対していつ有給休暇を取得するのか意見を聴取し、意見を尊重するように努めなければなりません。
尚、5日については使用者から時季指定した日、労働者が指定した日いずれも含めて問題ありません。そして、有給休暇時季指定義務違反(取得日数が5日未満)については30万円以下の罰金対象です。
また、2019年4月1日以降は「有給休暇管理簿」として有給休暇の発生基準日、労働者の取得総日数、実際に有給休暇を取得した日を管理しなければなりません。特に近年は新卒一括採用のみの雇用形態とは言い難く、中途採用もあり、法定の有給休暇と同様の労務管理を採用している場合は労働者ごとの管理が必要となります。
有給休暇管理簿は必ずしも紙で作成する必要はなく、電子機器を用いて作成することでも問題ありません。
有給休暇中の賃金
有給休暇中の賃金については以下の3通りがあり、どれを採用するのか就業規則に規定しておかなければなりません。
平均賃金
所定労働時間労働した場合支払われる通常の賃金
健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定の締結が必要)
実務上は所定労働時間労働した場合支払われる通常の賃金が採用されていることが多いのが現状です。
白石営林署事件
従業員が、年次有給休暇を取得して2日間出勤しませんでした。そして、年次有給休暇を取得した日は、他の事業所で行われたストライキの支援活動に参加していることがわかりました。そこで当該従業員が所属する事業所では、年次有給休暇を認めないで欠勤扱いとし、その日の賃金をカットしました。そこで、従業員が賃金カットは違法であるとし、カットされた賃金の支払いを求めて提訴しという事案です。
有給休暇は労働者が「請求」することとなっていますが、法律上は労働者が時季を「指定」することで足ります。すなわち、労働者が時季を指定した場合、使用者が時季変更をしなければ有給休暇は成立し、かつ、承認という概念が入り込む余地はないということです。
尚、労働者が所属する企業に対するストライキの場合は適正な有給休暇の行使ではないため、使用者は拒否することが可能ですが、所属事業場以外のストライキであるため拒否できる事案にはあたりません。よって、年次有給休暇は成立し、賃金の支払義務もあったという判決です。
様々な休暇
法定を上回る休暇

有給の夏季休暇などを法定の有給休暇とは別に規定を設けている企業も散見されます。当然、規定上労働基準法の有給休暇とは別に設けている場合は、年5日時季指定義務の中に含めることはできません。また、上記夏季休暇を法定の有給休暇に振り替える取り扱いも不利益変更にあたることから適正な労務管理ではありません。
また、法定の有給休暇は時効が2年となっており、多くの場合毎年全ての有給休暇を消化することは難しい場合が多いと考えます。そこで、2年を超えて時効消滅した有給休暇を積み立てて、特定の事由(例えば家族に介護を必要とする事情が生じたときのみに使用する)が生じたときのみ請求することができる「積み立て年休制度」という制度を設けている企業もあります。
法定の有給休暇は取得理由によって使用者が拒むことはできず、労働者がどのような理由で取得するかは使用者が逐一管理すべき部分ではありません。しかし、全く取得理由を聴くことができないかというとそうではありません。例えば複数の労働者から有給休暇の申請があった場合で、代替要員も確保できないような場合でやむを得ず双方の取得理由を聴く程度であれば違法とは言えません。
また、長く労働者として務めるということはその分様々なライフイベントが起こり得ます。冠婚葬祭などが代表例ですが、そこで、慶弔休暇として労働者の親族に慶事や弔事があった際に特別休暇として有給の休暇を与えることがあります。本来労働基準法上の年次有給休暇は例外(自社のストライキに参加)を除き取得理由は問われません。しかし、労働基準法の年次有給休暇とは別に特別休暇として有給の休暇を付与する場合は取得理由を限定しても問題ありません。そこでどのような場合に対象となるかを予め決定しておくべきです。また、同時に付与日数も決定しておくべきです。例えば自身の結婚の場合、祖父が他界した場合、それぞれ何日であれば取得可能かということです。そして、就業規則が整備されている企業の場合は規定として明記し、労働者に周知しておくことが重要です。
生理休暇
労働基準法第68条には「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として規定があります。賃金については、有給とするか無給とするかは当事者の裁量で問題ありません。
次に請求については、必ずしも暦日単位である必要はなく、半日または時間単位で請求した場合、使用者はその範囲で就業させなければ足りると解されます。そして、生理日の就業の困難さは各人によって異なるものであり、就業規則などによりその日数を限定することはできません。しかし、「有給」の日を定めておくことはそれ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差支えありません。
時季指定権と時季変更権
労働者から時季指定された日が「事業の正常な運営に支障をきたす」場合には使用者は時季変更権を行使することができます。尚、時季変更権はどのような場合も行使することができるわけではありません。時季変更権を行使できるのは、事業規模、繁忙度、職務、代替要員の確保状況、休暇期間の長短などを総合的に勘案して行使することとなります。また、時季変更権は有給休暇の時季指定を消滅させるという意味ではなく、取得時季を変更させるに留まります。よって、退職が予定されている労働者から有給休暇の時季指定があり、やむを得ず時季変更権を行使する場合、当然退職日を過ぎての時季変更権は行使できません。
休暇、休日、休業の違い

実務上似て非なるものとして、休暇、休日、休業の解釈があります。一つずつ確認しましょう。
休暇は就労義務がある日に、労働者が権利を行使することによって就労義務が消滅した日と解されます。
また、休日はそもそも就労義務がない日です。すなわち休日に休暇を指定するということは理論上あり得ません。
そして、休業については、就労義務がある日に使用者が就労をさせない日と解されます。
実務上、有給休暇の消化が進んでいない労働者に対して勝手に有給休暇を消化させるという取り扱いが散見されますが、あくまで労働者の時季指定があることが前提となります。
同一労働同一賃金
大企業では2020年4月1日からいわゆる同一労働同一賃金が施行されました。文言上は賃金のみと考えがちですが、過去の判例に照らすと休暇についても適正に労務管理を進めていかなければなりません。例えば夏季休暇について正社員に与えているにも非正規職員には与えていない場合の対応です。これは、夏季休暇をどのような目的で付与しているのかを明確にしなければなりません。また、判例はその企業にとっての裁判所の判断となり、自社と全く同一の背景での判例は稀と考えます。よって、そのまま参考にするのではなく、自社の体制に置き換えて考えることが重要です。
有給休暇の実務上の問題
有給休暇は企業によっても取得率が大きく異なります。当然零細企業の場合は代替要員の確保が容易ではなく取得が進まないことの一要因であることは想像に難くありません。しかし、大企業であっても有給休暇の取得が進んでいる企業もあれば、進んでいない企業もあります。これは取得しやすい雰囲気や有給休暇取得に関する周知啓蒙が進んでいるか否かが大きく影響していると考えます。有給休暇は単に労務の提供が免除されるだけではなく、心身のリフレッシュとその後の労働生産性向上に資することが挙げられます。よって、長期的には単に一日の休暇以上にプラスの効果が波及することもあります。

最後に
年次有給休暇は2019年4月1日付法改正後も多くの実務上の問題が浮上しており、かつ、労働者からの注目度も高い分野です。また、法改正部分だけでなく、疑義が生じた場合は専門家と連携しているアウトソーシング先を活用するなど、適正な労務管理が求められます。特に退職間際で有給休暇を発端としたトラブルが多くあり、事前法務が極めて重要と考えます。