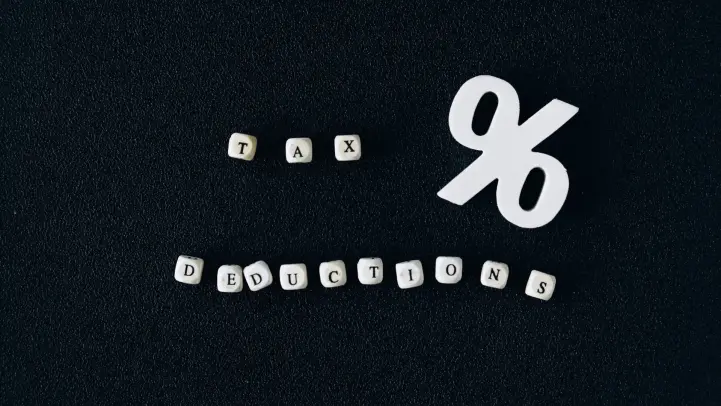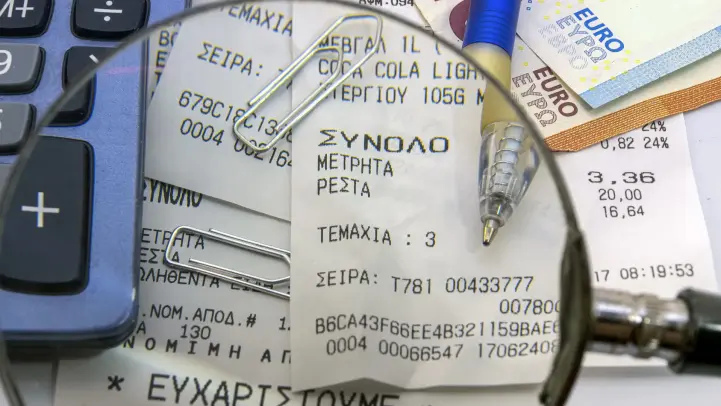妊産婦とは
妊産婦とは妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性です。妊産婦を雇用する場合、労務担当者として他の労働者とは違った労務管理が必要となります。密接した部分としては後述する産前産後休業や育児休業に関する説明を始め各種社会保険関連の手続きがあります。また、企業には安全配慮義務(労働契約法5条)が課せられ、妊産婦は旧来と同じように労務の提供ができるとは限らない状態となっています。よって、母体管理上も必要な措置を講じるためにその選択肢を準備しておく必要があります。
妊産婦を雇用する際の注意点を労働基準法を交えながら解説していきます。

坑内業務の就業制限(労働基準法)
妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は坑内で行われる全ての業務に就業させてはなりません。
また、上記に該当しない女性以外の18歳以上の女性については坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務に就業させてはなりません。
危険有害業務の就業制限(労働基準法)
使用者は妊産婦に重量物を扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就業させてはなりません。
産前産後休業(労働基準法)
出産の日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定である女性が休業を申し出た場合は就業させてはなりません。いわゆる産前休業であり、産後休業と異なる点としては女性労働者の請求が必要であることです。また、産後休業は女性労働者の請求の有無に関わらず出産日の翌日から8週間は就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が就労を請求し、かつ、医師が支障なしと認めた場合に就業させることは差し支えありません。
軽易業務への転換(労働基準法)
妊娠中の女性労働者が請求した場合、現在の業務よりも他の軽易な業務に転換させなければなりません。しかし、これは使用者として新たに軽易な業務を創設して与えることまで要求されているわけではありません。

妊産婦の就業制限(時間外労働等・労働基準法)
妊産婦が請求した場合、使用者は1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制を採用していたとしても週40時間、1日8時間を超えて就労させてはなりません。妊産婦であっても健康状態には個人差があり、画一的に請求があるとは断言できませんが、請求があった場合には応じなければなりません。
また、上記の変形労働時間制を採用しておらず、一般的な就労形態である場合はどのように労務管理を進めればよいのでしょうか。まずは時間外労働等を命じるには36協定を締結していることが前提となりますが、妊産婦が請求した場合は36協定を締結していたとしても時間外労働および休日労働をさせることはできません。また、深夜業についても妊産婦から請求があった場合は就労させてはなりません。そして、労働基準法第41条対象者(例えば管理監督者)については、労働時間、休憩、休日に関する規制が及ばないことから、時間外労働および休日労働については適用の余地はありません。しかし、深夜に対する規制は及ぶことから、請求があった場合には深夜業を命じることはできません。
フレックスタイム制と妊産婦
フレックスタイム制は本来、労働者に有利な制度であるため、妊産婦の就業制限の対象とはなっていません。
育児における基本事項
育児時間(労働基準法)
生後1歳に満たない生児を育てる女性労働者は1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。尚、当該時間を有給とするか無給とするかは労使間での取り決めとして問題ありません。

育児介護休業法とは
子供の養育等を容易にするため所定労働時間等に関して使用者が講ずべき措置を定めた法律です。妊娠、出産、育児は一朝一夕に完結するものではなく、長期間にわたって継続的に仕事と密接に関わっていくものです。そこで、雇用の継続や仕事と家庭の両立に寄与することを目的に様々な制度が創設されています。
まずは、産後休業が終了後に原則として1歳の誕生日の前日までの期間を育児休業期間として設定されています。しかし、申し込みをしたものの保育園に入園できない場合等は最長2歳までの育児休業が可能となります。(有期雇用労働者の場合等で労使協定によって育児休業自体が除外される場合あり)
男性における育児休業
育児休業の取得率は女性が80%超で推移しているものの、男性は10%にも及びません。これは社会的にも育児が女性に偏重していると考えるのが妥当です。そこで、男性の育児休業についてのメリットが周知され始めています。
パパ休暇とは
男性の育児休業はあまり知られていない部分ですが、2回取得することができます。そのうちの1回目をパパ休暇と呼びます。パパ休暇とは子供が生まれて8週間以内に育児休業を取得することです。尚、パパ休暇を取得し、間を空けて最後の育児休業を取得できることから、2回の取得が可能ということです。特に産後8週間は女性の身体的な負担が大きいとされる期間であり、注目されている制度です。

パパママ育休とは
原則として1歳の誕生日の前日まで取得できる育児休業ですが、両親がともに育児休業を取得し、以下のいずれの要件も満たした場合には、1歳2か月に達する日の前日まで育児休業を取得できる制度です。
・配偶者が、1歳の誕生日の前日以前に育児休業を取得している
・本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降である
・本人の育児休業開始予定日が1歳の誕生日以前である
尚、1人当たりの育児休業取得可能最大日数は1年間である点は変わりません。この制度のメリットは、可能な限りいずれかの親が子育てに携われるという点と、後述する育児休業給付金においても恩恵を享受することができる点です。
育児休業給付金
毎月の給与から徴収されるものの中に雇用保険料があります。雇用保険への加入は週20時間以上の労働かつ、31日以上の雇用見込みであれば加入しなければなりません。そして育児休業に入り、所定の要件を満たした場合はハローワークから育児休業給付金から支給されます。尚、育児休業給付金の額は休業開始前の6ヶ月の賃金を180で除した金額が休業開始時賃金日額として算出されます。
その日額と育児休業を取得した日数に67%を乗じた金額が1ヶ月あたりの育児休業給付金となります。しかし、休業開始後6ヶ月(181日目)後からは67%の割合が50%へ変更となります。
パパママ育休制度を活用するメリットとして、母親が育児休業給付金の支給割合が50%に下がる前に復職し、父親がパパママ育休制度を活用して、家計単位では育児休業給付金が67%を受け続けることで、収入面での不安も和らげることができます。
社会保険料免除について
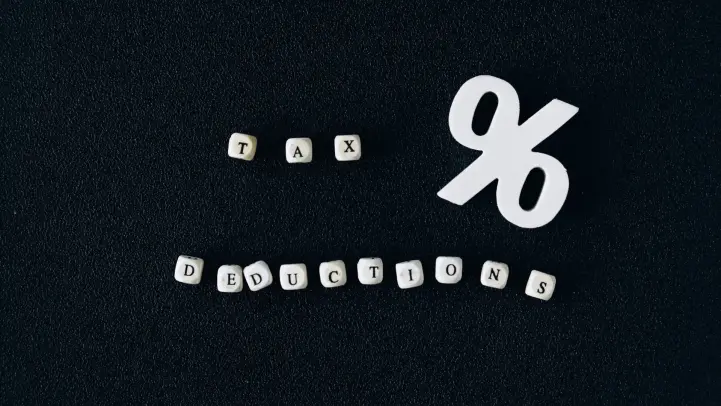
産前産後休業期間
産前産後休業期間における社会保険料免除の制度があります。当然、男性には産前産後休業はありませんので、女性のみの制度となります。期間は産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間となります。
尚、代表取締役は産前産後休業期間における社会保険料免除は適用されますが、後述する育児休業期間における社会保険料免除の規定は適用されません。
そして、保険料免除は労働者だけでなく使用者も免除対象となり、将来の年金受給の際にも産前産後休業期間における社会保険料免除期間は後述する育児休業期間における社会保険料免除期間とともに通常の保険料納付期間と同様の扱いとなります。ゆえに年金額計算においても当該期間が不利に働く(免除期間分の年金額が減額される)ことはないという理解です。
育児休業期間
産前産後休業期間における社会保険料免除期間と同様の恩恵を享受することができますが、期間を確認しましょう。育児休業を開始した日の属する月から育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月までとなります。
尚、育児休業期間における社会保険料免除制度は女性だけでなく、男性にも適用されることから、労務担当者はおさえておく必要があります。
手当や一時金、その他の注意点
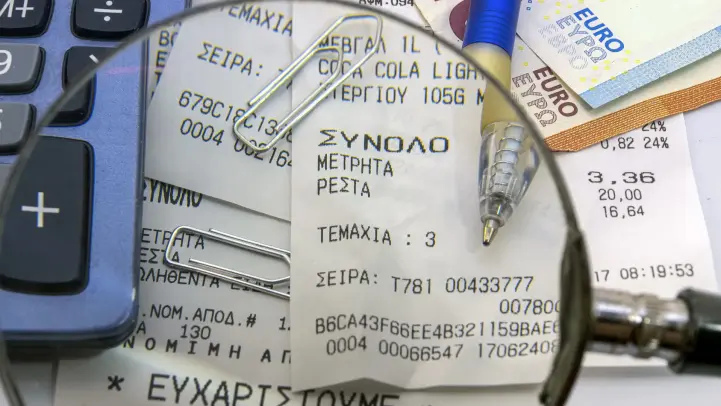
出産手当金
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間が出産手当金の支給対象期間となります。支給額は直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2となります。しかし、規定により産前産後休業期間中は全額給与支給となっている場合は不支給となります。また、全額給与支給とまではいかずとも一定額給与が支給される場合は、調整された額で支給される場合があります。しかし、給与の額が出産手当金を上回る場合、出産手当金は全く支給されません。
出産手当金と傷病手当金の関係
出産手当金と傷病手当金の両方が支給される場合は、出産手当金が優先的に支給されます。
出産育児一時金
出産育児一時金は出産をした場合に一時金として一児につき42万円が支給されます。尚、出産育児一時金は胎児数に応じて支給されます。
産前産後休業を終了した際の標準改定
固定的給与が大幅に変動した場合に随時改定として、給与実態に合致した社会保険料となるように改定する制度があります。しかし、随時改定は3か月連続して給与の支払い基礎日数が17日以上であること、2等級以上の変動があることなどの要件があります。
しかし、産前産後休業を終了した際の改定は1等級以上の変動があること、少なくとも1ヶ月は給与支払い基礎日数が17日以上であることを満たせば適用が可能となります。
育児休業を終了した際の改定
育児休業を終了した際の改定も産前産後を終了した際の改定と同様の定めがあります。

3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
例えば育児休業復帰後の働き方と育児休業前の働き方では保育園への迎えの関係で残業や夜勤ができなくなったケースがあり、給与も実態として減っていることが多いでしょう。その場合に、給与額に見合った保険料に改定し、将来受け取る年金額の計算においても給与が減る前の投球で計算をするという特例的な制度があります。
資格喪失後の給付
被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている場合は継続給付として資格喪失後も出産手当金が支給されます。しかし、有給であったことから出産手当金の支給が停止されている場合はどのように考えるのでしょうか。この場合は事業主から給与が支給されなくなった時から支給が開始されます。
尚、資格喪失後の継続給付については、1年以上被保険者であった者という要件もあります。
妊娠、出産、育児を踏まえた労務管理
労働関係法令、社会保険諸法令、多くの法律では妊娠、出産、育児に関する規定が存在します。特に罰則が付される労働基準法では労務担当者が押さえておかなければならない規定が複数あり、社会保険諸法令でも手続きが遅かったがゆえに本来受けられるはずであった給付が時効消滅による受けられなかった場合も問題となります。これらの労務管理は、特に女性労働者を雇用する場合は継続的に発生し得ることから、フローチャートやチェックリスト化して漏れのないように進めていきたい部分です。
最後に
出生数の減少は少子高齢化社会の解消にも影響必須の問題であり、政府としても看過できない状況です。よって、今後も特に男性向けの育児に関する法整備等が予想され、労務担当者としてはそれらの改正情報も随時キャッチアップしていく必要があります。特に改正のスタートが決まっているもの、経過措置が置かれるものなども峻別しておさえておく必要がり、必要に応じて専門家と連携しているアウトソーシングを活用するなどの選択も重要です。
また、マタハラなど、妊婦に向けられたハラスメントがあることも事実であり、訴訟にまで発展している事案もあります。事業場内での周知啓蒙など単に法律を理解するだけでなく職場内の環境整備をすることも労務担当者として重要な職務となります。