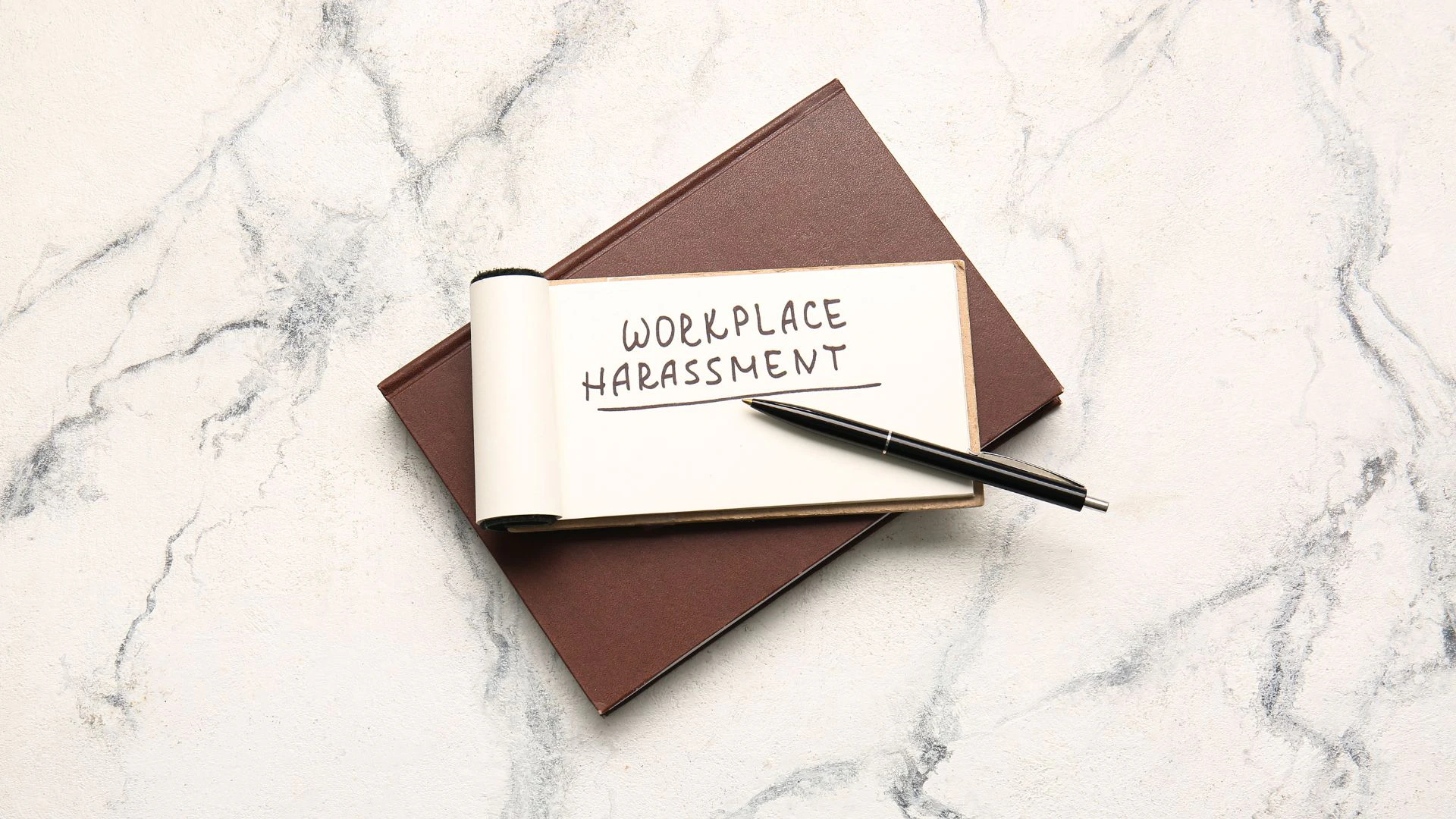対面面接とオンライン面接のメリット・デメリット
面接には対面とオンラインの2つの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、詳しく見ていきましょう。

対面面接
旧来から最も多く採用されている対面型の面接です。事前に時間と場所を特定し、面接官と同じ空間で面接を行います。労務管理上注意すべき点は事前に電話で時間と場所を伝える場合に相手に正確に伝わっているかの確認をすべきです。メールで連絡する場合は後で読み返すこともでき、双方確認がいつでも何度でも確認が取りやすいという利点がありますが、電話の場合は留守番電話にメッセージを残す場合を除き、その時しか確認が取れません。しかし、メールではなく電話をすることで、求職者の声を聞くことができ、場合によっては履歴書に書かれた文字以上に人となりを把握することができます。よって、電話で面接日程を伝える場合は求職者に確実に伝わっているかの確認(電話を切る前に再度の確認を取る)には極めて重要です。
そして、対面面接では当然、時間だけでなく場所も拘束されることから中小企業の求人に多くの応募がった場合には一定時間、面接官を拘束するだけでなく、面接場所の確保が必要です。メリットとしてはオンライン以上に求職者を肌で感じることができ、オンライン面接と比べてミスマッチを防ぎやすいと言われています。
オンライン面接
オンライン面接は対面面接と比べてトラブルへの対処法を熟知しておく必要があります。突然通信が途絶えた場合が代表的であり、企業側だけでなく、求職者側の問題で通信が途絶えることも想定されます。後ろに次の求職者がオンライン面接を控えている場合、対面と比べて求職者自身が「面接会場」がどのような状態になっているか確認がしづらく、不安感に苛まれてしまうことは想像に難くありません。また、オンライン面接は対面と比較すると等身大の求職者を肌で感じることができず、ミスマッチが生まれやすいとの指摘がありますが、求職者目線では面接会場までの宿泊費や通勤費用がかからず、地方の有能な求職者も採用対象とすることができるメリットは大きいと言えるでしょう。
また、オンライン面接の場合は、対面での面接と比べて求職者から録画されている可能性が高いと言えます。よって、重要な労働条件を示す時は注意を払うべきであり、誤解の生じやすい発言には十分注意することが求められます。
選考の方法、適切な質問内容、求職者の評価
面接の前に行う書類選考のポイントや、面接時の質問内容や注意事項をまとめました。これらのポイントを理解し適切に対応することが成功する面接の鍵となります。

書類選考
面接前には書類選考を行うことが通例です。ここでは各々の企業で求める人材像であるか否かを書類で選考します。書類選考通過後は面接日程の調整へ移りますが、履歴書は個人情報にあたるため、その取り扱いは慎重に行わなければなりません。
アイスブレイク
面接官としては面接の中で可能な限り求職者の本来の姿を見て、採否を決断したいことですが、緊張から本来の力を発揮できず、面接を終える例も少なくありません。そこで、アイスブレイク(緊張をほぐすための雑談)を入れることで、求職者の緊張感を解き、その後に本題の質問に入るという手法を取り入れることも多くなっています。
質問するに相応しくない内容
厚生労働省では、面接において以下の質問をすることや応募用紙に以下の内容を含んだ記載をさせることは就職差別に繋がる恐れがあるとして、周知されています。
本人に責任のない事項の把握
- 本籍、出生地に関すること (「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当)
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(家族の仕事の有無、職種、勤務先などや家族構成はこれに該当)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境、家庭環境などに関すること
本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
採用選考の方法
- 身元調査などの実施 (「現住所の略図」は生活環境などを把握することから身元調査につながる可能性がある)
- 合理的、客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
当然、司法の争いにまで発展した場合、上記の質問をしたことが必ず違法と判示されるとは断言できませんが、少なくとも行政から各企業への周知であり、望ましくない質問であることは留意しておくべきです。
事実確認
まずは、履歴書に記載されている内容の事実確認をすることが適切です。滅多に起こることではなく、その前に気付くことでもありますが、複数の求職者が面接に訪れている場合、事前に面接官が保持している履歴書の順番と入室した求職者の順番が相違している可能性も否定できないからです。面接の後半に確認するのもおかしな話であるため、冒頭で確認しておくことが適切でしょう。
キャリアパス
今後どのようなキャリアパスを描きたいのかを求職者に聴くことです。具体的な回答があれば、少々困難な道であっても忍耐強く誠実に勤めてくれることが期待できると考えます。しかし、人員の関係で希望通りの部署での勤務が約束できない場合は発言内容には注意が必要です。また、中途採用で職種や地域限定採用を行う場合は採用後に職種転換や転勤については同意が必要であり、双方で認識齟齬がないように注意が必要です。
条件確認
採用後の労働・福利厚生の条件は労働者にとって極めて重要なものです。当然口頭のみでは時間が経過した時に記憶が曖昧となるために、書面にて双方が確認できる形であることが適切です。また、賞与など景気の変動を多分に受けるものに関しては支給額や支給率を確定的に明示してしまうと、万が一支給できなかった場合(支給額が少なかった場合も)トラブルに発展する可能性があります。
オープンクエスチョン
面接では面接官から求職者に対して質問を行いますが、クローズドクエスチョン(イエスまたはノーで答えられる質問)よりもオープンクエスチョンを用いる方が求職者の人となりが把握できます。面接では面接官の事前準備によっても成否が別れることは多々あります。オープンクエスチョンに対する回答は言葉遣いの随所に知性が見え隠れし、最終的な話のまとめ方など多くの選考箇所が生まれます。
逆質問
面接終盤には面接官に対しての質問(逆質問)を用いる企業もあります。多くの場合、残された短い時間の中で全く興味のないことを質問する求職者はいないでしょう。また、逆質問されることを予測して準備しているケースも多いとは言えず、求職者の本心から出されるものであり、何を思っているのか、または何が気になっているのかを確認できる数少ない機会とも言えます。
転職理由
中途採用者の場合、転職するに至った背景は必ず存在します。ネガティブな理由もあればキャリアアップのためというポジティブな理由もあります。特にネガティブな理由の場合は本人に帰責事由(例えば会社側の倒産)がない場合もありますが、終始ネガティブな意見を述べるのと、そこから問題を解決しようとする姿勢を示す求職者では全く印象が異なります。また、ネガティブな話をする際の語調や表情などを観察することで対人折衝力を判断する際の要素になるでしょう。
ストレスコントロール
コロナ禍を経て、対面での業務やリモートでの業務など、ハイブリッド型の労務提供が一般的になりつつあります。そのような時代であっても対人関係は必要不可欠な能力と言えます。対面業務であれば、他者への配慮が必要であり、リモート環境の場合は対面業務以上に伝達能力やコミュニケーションスキルは必要となります。現代のように目まぐるしく「常識」が変わる中、ストレスフリーで業務を続けていくことは極めて困難です。よって、自身のストレスをどのようにコントロールしていくのか、中途採用者であればどのような時にストレスを感じていたのか、ストレス耐性を見極める意味でも意味のある質問となります。
対人関係
コロナ禍以降は人と人とが手の触れ合う距離でのみで仕事をする時代ではなくなりました。ストレスコントロールでも述べたとおり、離れている環境でもどのように相手に正確に物事を伝えるか、また、齟齬が生じた場合のフォローなどは必須のスキルです。AIが普及していく時代であっても人が全くいない状態でビジネスが発展していくことは難しいでしょう。
オワハラについて
就職活動を終わらせるような言動を発することを「オワハラ」と呼びますが、本来求職者には職業選択の自由があることから、あまりにも行き過ぎた発言は職業選択の自由を侵害するに留まらず、レピュテーションリスクが顕在化してきます。昨今はSNS等を通じて簡単に情報が流れる時代であることから、この点には十分留意すべきです。また、オワハラにより入社したとしても既に信頼関係に亀裂が生じていることも珍しくなく、早期離職を招くなど長期的には企業にとってマイナス面も指摘されています。
面接の進行や選考における注意点
面接の際に良い人材を採用するために確認すべきポイントと、面接官としての心得についてご紹介します。

面接前の到着時間
常識的には10分前に到着していれば問題ないと言えるでしょう。また事情は様々あるものの遅刻する場合は連絡の有無は無視できません。また、30分近く早く到着するもの相手のことを考えれば適切な行動とは言い難いことから面接前からも事実上の選考は始まっていると考えます。
募集人材と合致しているか
中途採用であればどのような目的で募集をかけるのか、複数の面接官で面接に臨む場合は目的を共有しておくことが重要です。単に学歴だけで選考するなど、募集目的と合致しているとは言い難い決断はミスマッチが起こる可能性があります。
必要なスキルを有しているか
中途採用の場合、募集する職種によって必要なスキルは様々です。募集するに至った背景を揺るがすことなく、フラットな視点で選考することが重要です。
面接官は広告塔
本来、面接官は求職者の人物像を観察するのが役割ですが、面接官も見られているという意識を持つべきです。これは、求職者に不快感を与えるような言動をしてしまうと、いくら受付等で好感が持てる企業であっても帳消しになってしまうからです。また、受付担当者よりも面接官との方が多くの時間を過ごすことから、会社としてのイメージに多大な影響を及ぼします。
また、面接官にとっては複数の応募があった場合は、それほど印象には残らないこともあるでしょう。しかし、求職者からすると対面面接で感じる印象は1回であり、印象の大きさも比較にはなりません。
カルチャーマッチ
カルチャーマッチとは社員が企業理念や文化に共感し、適合していくことを指します。企業理念や文化は頻繁に変わるものではなく、会社の根幹であり、価値観が相違したまま労務の提供を行っていくことは労使方法にとって有益とは言えません。求人票作成や採用面接の段階で企業理念は明確に示して、どのような反応を示すかは確認しておきたい部分です。